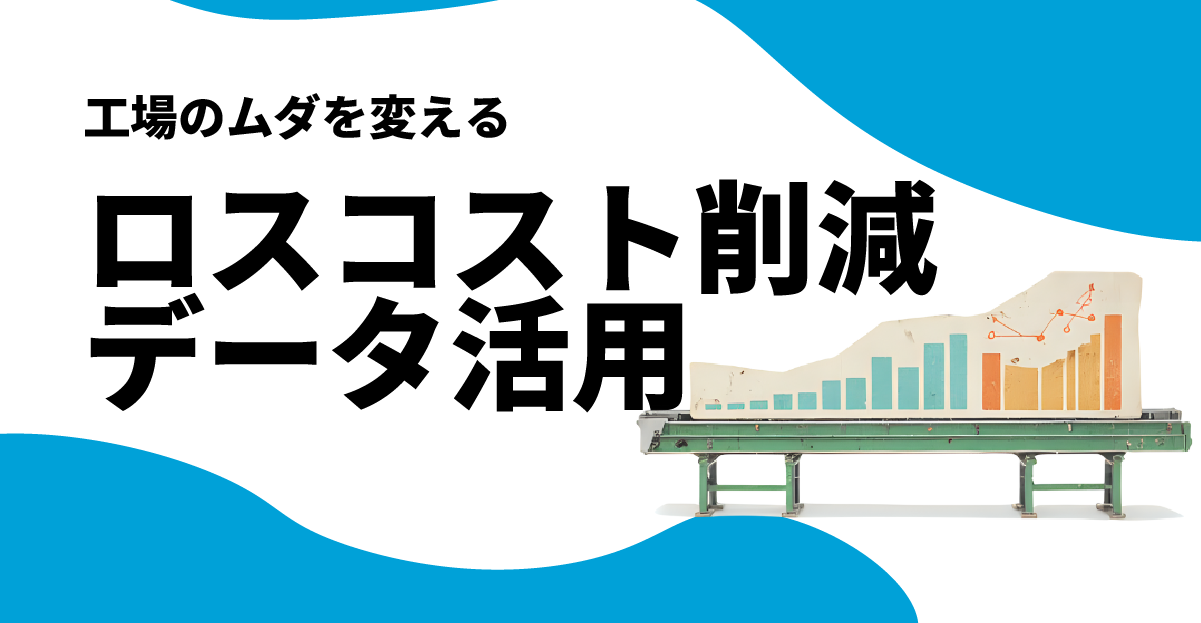
ロスコスト削減とデータ活用の5ステップ|工場のムダを利益に変える方法
なぜ今「ロスコスト削減」なのか?
製造業において、品質不良、設備停止、材料ロス、手戻り、在庫過多など、直接的な利益を生まない「ロスコスト」は、企業の収益構造に大きな影響を与えています。経済産業省の工業統計調査によると、売上原価のうち5〜15%がロスに該当するとされており、企業によっては年間数千万円〜数億円規模の損失につながることもあります。このようなロスコストは、現場の勘や経験だけでは見つけにくく、改善の優先順位も曖昧になりがちです。
そこで注目されているのが、データ活用による「見える化」と「即時対応」です。製造現場には、設備稼働ログ、品質検査結果、作業時間、在庫状況など、膨大なデータが眠っており、これらを分析することで、隠れたロスの要因を特定し、改善につなげることが可能になります。
本コラムでは、ロスコスト削減とデータ活用を組み合わせた「儲かる工場」への実践ステップを、成功事例とともにご紹介します。
目次[非表示]
見える化すべき『ムダ』の正体
製造現場におけるロスコスト削減を進めるうえで、まず着目すべきは「ムダ」の正体です。現場の感覚だけでは捉えきれないムダを、体系的に分類・可視化することで、改善の優先順位が明確になります。
リーンシックスシグマ(トヨタ生産方式に由来する「リーン(Lean)」のムダ排除思想と、モトローラが開発した「シックスシグマ(Six Sigma)」の統計的品質管理手法を融合した改善アプローチ)では、以下の8つのムダが定義されており、それぞれが利益を圧迫する要因となります。
- 過剰生産 :必要以上に作ることで在庫や廃棄が増え、資源が無駄になる。
- 待ち時間 :作業や工程の間に発生する待機が、生産効率を低下させる。
- 不必要な搬送:製品や部品の過剰な移動が、時間とコストを浪費する。
- 過剰な加工 :仕様以上の加工や検査が、付加価値を生まないコストを増やす。
- 在庫 :過剰な在庫は保管費用や陳腐化リスクを高め、資金を圧迫する。
- 不必要な動作:作業者の無駄な動きが、作業時間の非効率化を招く。
- 不良品 :品質不良による手直しや廃棄が、直接的な損失を生む。
- 未活用の人材:スキルや知識が活かされないことで、組織の潜在力が損なわれる。
これらのムダをデータで「見える化」することが、ロスコスト削減の第一歩です。現場の改善活動を加速させるためにも、ムダの構造を理解し、定量的に捉える視点が求められます。
よくある課題:分析が定着しない理由とは?
多くの製造業では、データ分析の重要性を認識しながらも、現場への定着に苦戦しています。その背景には、技術的な課題だけでなく、組織文化や人材面の要因が複雑に絡み合っています。
よくある課題①:属人化
まず、分析業務が特定の担当者に依存している「属人化」の問題があります。ExcelやBIツールを使った分析が個人のスキルに依存しているため、担当者が異動・退職するとノウハウが失われ、改善活動が停滞するケースが少なくありません。これにより、分析結果の再現性が乏しく、組織としての学習が進まないという課題が生じます。
よくある課題②:導入したツールの不適合
次に、導入されたツールが現場の業務フローに合っていない「ツールの不適合」も定着を妨げる要因です。操作が複雑であったり、現場のITリテラシーに合っていない場合、ツールが使われずに放置されることがあります。特に、現場では「使いやすさ」や「即時性」が求められるため、UI/UXの設計やモバイル対応など、現場目線でのツール選定が不可欠です。
よくある課題③:ROIが不明瞭
さらに、「ROI(費用対効果)の不明瞭さ」も大きな障壁です。分析活動の成果が定量化されていないと、経営層からの評価が得られず、継続的な投資が難しくなります。現場主導で進められた改善活動が経営戦略と連動していない場合、組織全体としての推進力が弱くなり、分析が一過性の取り組みに終わってしまうこともあります。
よくある課題④:現場と経営層の目的が異なる
また、現場と経営層の間にある「目的のズレ」も見逃せません。現場は日々の業務改善を重視する一方で、経営層は中長期的な利益改善やKPI達成を重視する傾向があります。このギャップを埋めるためには、分析の目的や成果を双方が共有し、共通のゴールに向かって取り組む必要があります。
これらの課題を乗り越えるためには、技術・人材・組織の3つの視点からバランスよく対策を講じることが重要です。具体的には、分析テンプレートの標準化や教育コンテンツの整備による属人化の解消、現場の声を反映したツール選定、そして成果の定量化と経営層への報告体制の構築が求められます。
パナソニックISでは、こうした課題に対して、現場定着支援や分析テンプレートの提供、経営層向けの成果報告支援などを通じて、データ活用の定着と成果創出を伴走しています。
実践ステップ:ロスコスト削減 × データ活用の5ステップ
ロスコスト削減とデータ活用を両立させるためには、以下の5つのステップが有効です。

ステップ1. ロスの見える化
センサーデータや業務記録を収集・分類し、課題を明確化。工程ごとの不良率や稼働率をリアルタイムで把握することで、改善の優先順位を明確にします。
ステップ2. 分析の標準化
ExcelやBIツールを活用し、分析指標や算出ロジック・ダッシュボードを標準化。共通の物差しの導入により、現場間の比較や横展開が容易になります。
ここでの進め方には2つのアプローチがあります。
既存のExcelや導入済みBIツールを活用する方法
新規投資をせずに可視化を始められるため、スモールスタートが可能です。先に導入するツールを決定し、その環境でテンプレートを作る方法
将来の再構築が不要になり、作成したテンプレートをそのまま活用できる利点があります。
ステップ3. 改善サイクルの設計
KPIと連動したPDCAサイクルを構築。分析結果をもとに改善策を立案し、実行・評価・再分析を繰り返すことで、継続的な改善が可能になります。
ステップ4. ツールと人材の整備
操作性の高いツールと現場教育を導入。現場が自律的に分析できる環境を整えることで、定着率と活用度が向上します。
ステップ5. 成果の定量化と展開
削減額・工数・品質向上などを数値化し、他ライン・他工場への展開へ。経営層への報告資料としても活用できる形で成果を整理することが重要です。
ロスコスト削減を解決するカギはデータ活用|資料ダウンロードはこちら
成功事例:パナソニックISが支援した2つの現場
弊社が支援した2つの事例をご紹介しましょう。
事例①:工程品質の見える化と即時対応
課題 :現場の状況が見えず、対応が遅れる。紙帳票では過去事例の活用も困難。
目標 :日々の品質や稼働を見える化し、即日対応でロス削減。
活用データ:生産計画、工程不良実績、作業履歴など
分析内容 :不良発生時刻やライン、部品情報をPower BIで可視化。アラート通知も実装。
成果 :工程品質を半減、 稼働ロス削減、対応スピードをDailyベースに短縮。他工場への展開も実現。
事例②:1ロット数千万円のロス削減。グレーゾーンをなくし保留・廃棄コスト回避
課題 :品質NGの原因が不明な場合、ロット全体を保留・廃棄。
目標 :品質に問題のない製品を迅速に特定し、ロスを回避。
活用データ:トレーサビリティ、センサーデータ、不良検知データ
分析内容 :相関分析により、問題のない製品を科学的に特定。ビッグデータ処理基盤も構築。
成果 :1ロット数千万円のロス削減。製造条件の見直しにも貢献。
まとめ:儲かる工場は「データで動く」
ロスコスト削減は、単なるコストカットではなく、現場と経営をつなぐ「儲かる工場」への第一歩です。小さな改善から始め、成果を定量化して横展開することで、全社的な利益体質の強化につながります。
本来であれば、こうした取り組みを社内の人材だけで完結できるのが理想ですが、データ分析スキルの習得には一定の教育期間が必要であり、専門人材の採用コストも高止まりしているのが現実です。そのため、知見と実績を持つ外部の専門家とタッグを組むことも、実効性とスピードの両面で有効な選択肢となります。
パナソニックISでは、こうした取り組みを支援するテンプレートや教育支援、分析基盤の構築サービスを提供しています。ご興味のある方は、ぜひお気軽にご相談ください。




