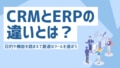SFAとは?活用するメリットや導入時のポイントについても解説
SFA(営業支援ツール)は、案件情報や商談の進捗状況といった営業情報をデータとして蓄積・管理し、営業活動を効率化するSFAツールです。営業担当者個人のスキルに依存しがちな営業活動を組織的に強化し、売上向上を目指す企業にとって不可欠なシステムとなりつつあります。
SFAには、さまざまな機能があり、数多くのベンダーがSFAを開発しているため、活用方法や選び方がわからないとお悩みの方も多いのではないでしょうか。まずはSFAについて基本的な理解を深め、導入後のイメージを持つことが大切です。
本記事では、SFAの機能や役割、導入するメリットについて詳しく解説します。導入・運用時のポイントも紹介していますので、ぜひ参考にしてください。
目次[非表示]
SFAとは

SFAとは「Sales Force Automation(セールス・フォース・オートメーション)」の略で、日本語では「営業支援システム」や「営業支援ツール」などと訳されます。その名の通り、営業担当者の活動を支援し、組織全体の営業力を強化するためのシステムです。具体的には、日々の営業活動で生まれる顧客情報、案件の進捗、商談内容といった営業情報を一元管理・分析することで、営業プロセスの可視化や自動化を実現します。
案件やリードに関する情報を一ヵ所に集約することで戦略的な営業活動が可能になるだけでなく、パイプライン構築や売上予測といった業務効率化のための機能も充実しています。
SFAの導入によって、営業マネージャーが営業活動を案件や担当者別にリアルタイムの状況を把握できるため、より適切な目標設定や人員配置、営業担当者へのフォローなどが可能になります。また、現場担当者は、外出先からでも顧客情報へアクセスができるようになり、データ入力や日報といった定型業務の効率化が可能です。
SFAの機能・役割
ここでは、SFAの機能や役割を解説します。具体的な機能や役割をイメージできれば、SFAの導入による効果をイメージしやすくなるでしょう。
SFAの主な機能
まずは、SFAに搭載されている代表的な機能を紹介します。
- 案件管理
- 顧客管理
- 行動・活動管理
- 予実管理(売上予測)
案件管理
取引先や営業活動の進捗状況を可視化できる機能です。案件ごとに次のような情報がシステムに記録されます。
- 担当者名
- 取引先名・取引先ID
- 顧客種別(潜在顧客・見込み顧客・既存顧客など)
- 見積金額
- 受注見込み日
- 進捗率
- ステータス(課題特定・アポ保留・条件面合意など)
- 失注理由
案件管理は正確な目標達成度を把握するのに便利な機能です。見込み金額や成約までのスケジュールがリアルタイムに把握できるため、予算の追加やアプローチ方法の変更などを状況に合わせて検討しやすくなるでしょう。
リード・顧客管理
リード(見込み顧客)の詳細な情報を一元管理できる機能です。
レコードに設定できる項目の種類はツールによって異なりますが、主に次のようなリード情報をシステム内へ集約できます。
- 取引先名・取引先ID
- 取引先企業の担当者名・年齢・性別
- 取引先企業の所在地
- 商談履歴
- アプローチ履歴
- 成約確度
SFAでは、見込み顧客の情報と案件情報を自動的にマッピング(紐付け)することが可能です。ツールによっては、CSVファイルをアップロードするだけで、データのインプットとマッピングが完了するタイプも存在します。
また、近年主流のCRM(顧客管理システム)統合型のSFAなら、見込み顧客が既存顧客へと転換したあとの情報についてもワンストップで管理できます。
見込み顧客の情報と既存顧客情報が別々に管理されている場合、問い合わせ履歴や製品に対するフィードバックといった重要な情報が、顧客情報にうまく紐づかないことがあります。CRMは、自社と接点がある個人や企業に関する情報を一元管理できるため、「見込み顧客」「既存顧客」などのステータスが変わっても情報が失われることがありません。
行動・活動管理
ファーストコンタクトから受注へと至る営業プロセスを一元管理するための機能です。「パイプライン管理機能」とも呼ばれています。
営業活動の簡易的なステータスは、案件管理機能からでも確認できますが、行動・活動管理機能は、担当者ごとの行動フローを詳細に把握できます。そのため、リアルタイムの進捗状況をもとに滞留が生じているフェーズや、将来的に遅延が発生しそうな箇所を正確に把握できるのが利点です。
営業マネージャーは、課題が発生している箇所へ適切にリソースを配分したり、迅速なフォローを行ったりできるため、マネジメント業務の効率化につながります。また、過去に難航した商談の内容や、失注に至った要因などを分析できるメリットもあります。
予実管理(売上予測)
システム内に蓄積された目標値と実績データを比較し、正確な売上予測を行える機能です。一般的にSFAには、次のような売上予測情報を記録できます。
- 部門やチーム全体の目標金額
- 成約に至った商談の合計金額
- 成約が確実な商談の合計金額
- 成約の可能性が高い商談の合計金額
- 未完了状態の商談の合計金額
また、売上予測金額を担当者や期間などの基準で分類できるのも特徴です。売上に対する貢献度を担当者ごとに分析することで、人事評価に役立てられるのも大きなメリットといえます。
CRMやMAとの役割の違い

ここでは、SFAと役割が混同されやすい「MA(マーケティングオートメーション)」や「CRM(顧客管理システム)」との違いを解説します。いずれも、営業・マーケティングに役立つツールですが、役割や目的が異なります。
ツール | 役割 | 目的 |
SFA | 営業活動の効率化を図るためのツール | 営業活動における情報の記録・共有 |
MA | 効率的なマーケティング活動を実現するためのツール 見込み顧客の獲得・育成 | 見込み顧客の獲得・育成 |
CRM | 顧客との関係性を管理するためのツール | 顧客との長期的な関係構築 |
MAとの違い
MA(マーケティングオートメーション)とは、マーケティング活動の一連の流れを効率化・自動化するためのツールです。広告連携やランディングページ作成、メール配信、スコアリングなどの機能が搭載されています。リード獲得から購買意欲の醸成、営業部門への送客までに至るマーケティングプロセス全体で、幅広い機能を活用できるのが特徴です。
一般的に、MAは「商談化する前」の見込み顧客の育成を、SFAは「商談化した後」の案件管理や営業活動の記録を担当します。MAでスコアリング(点数付け)によって購買意欲が高まったと判断された見込み顧客をSFAに引き継ぎ、営業担当者がアプローチするというのが、両者を連携させた際の基本的な流れです。
SFAとMAは連携することで、それぞれのツールの利点を最大限に活用できます。特にBtoBの領域では、マーケティングやインサイドセールスによって見込み顧客の確度を高め、その後は営業にてクロージングを行うケースが多いため、部門間のスムーズな連携がポイントになります。SFAとMAの連携によって部門の垣根を越えてリード情報を共有できるようになり、より適切なアプローチが可能になるでしょう。
CRMとの違い
CRMは「Customer Relationship Management(顧客関係管理)」の略で、既存顧客を含むすべての顧客との良好な関係を長期的に築き、LTV(顧客生涯価値)を最大化することを目的としたツールです。
SFAが商談や案件といった「営業プロセス」の管理に重点を置くのに対し、CRMは顧客情報や過去の対応履歴といった「顧客」そのものの管理に重点を置くという違いがあります。
システム内には、顧客の属性や行動履歴などの多様なデータを集約できます。蓄積されたデータから顧客のニーズを読み解くことで、営業・マーケティング戦略の最適化や、商品・サービスの品質向上に寄与します。
SFAにも見込み顧客の情報を集約できるリード管理機能が搭載されていますが、成約後の顧客との接触履歴も管理するためには、CRMとのシステム連携が必要です。ただし、SFAとCRMは役割が重なる部分もあるため、最近ではCRM機能を標準搭載したSFAも数多くあります。
SFAを導入するメリット
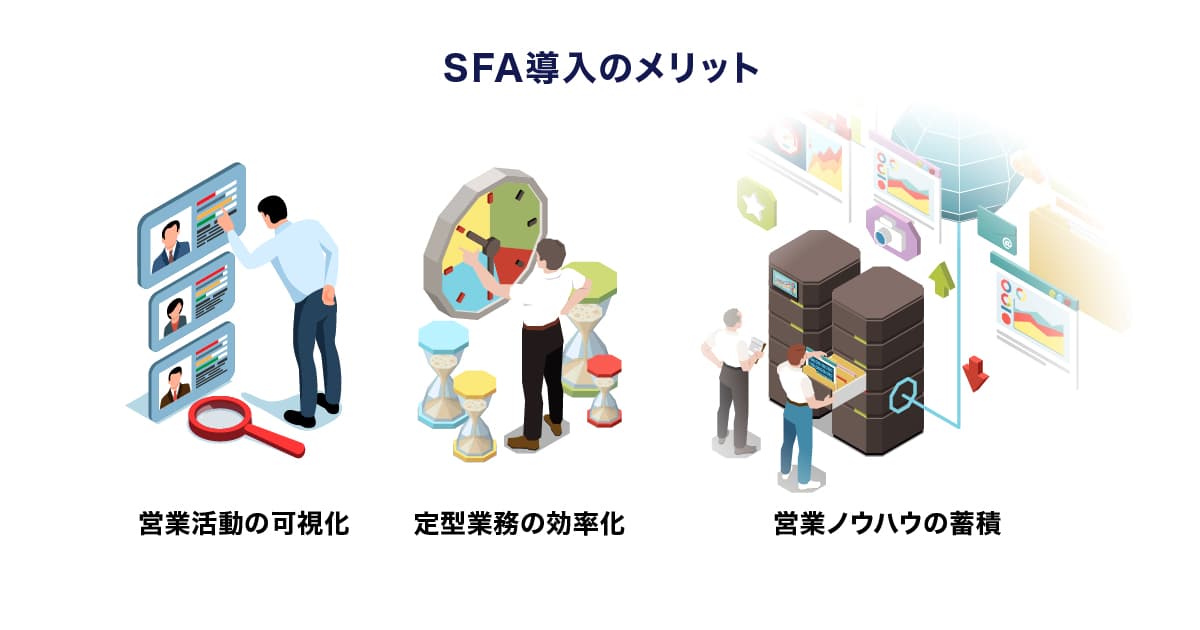
SFAを導入することで、営業活動の可視化や定型業務の効率化といった、さまざまなメリットが生まれます。ここでは、SFAの導入によるメリットを具体的に解説します。
営業活動の可視化ができる
SFAには案件管理や行動管理など、リアルタイムの活動状況がわかる幅広い機能が搭載されています。案件や担当者別に見込み顧客の状況や商談の進捗状況を部門全体で共有できるため、業務上の課題を見つけやすくなります。
また、情報管理の属人化が解消されることで、重複対応や対応漏れの回数が減少するのもメリットの一つです。見込み顧客や既存顧客の状況に合わせて的確なアプローチを行うことにもつながり、成約率の改善や既存顧客との関係強化が実現できるでしょう。
営業における定型業務の効率化ができる
SFAは情報管理機能以外にも、営業活動の効率化をサポートする機能を備えています。
モバイルアプリに対応したSFAなら、外出先から日報作成やデータ入力を行えるため、隙間時間を有効に活用できるでしょう。地図アプリと連携できるSFAもあり、営業ルートの検索やスケジュール管理に役立ちます。
さらに近年は、AI技術の向上により、簡易的な定型業務を自動処理できるSFAも登場しています。こういったツールは、あらかじめ業務フローを設定することで、トリガーを起点に定型業務の自動処理が実行される仕組みです。
営業活動におけるノウハウを蓄積できる
社内のナレッジベースとして活用できるのも、SFAのメリットの一つです。
SFAは営業活動に関するあらゆるデータを集約し、部門全体で情報を共有できます。失注理由の分析や、成績上位の営業担当者のノウハウなど、定量・定性情報を社内ナレッジとして蓄積できるのがポイントです。
結果として、営業スキルの均質化を図れるほか、教育コストの削減にもつながります。
SFAを導入・運用する際のポイント
ここでは、SFAを導入・運用する際のポイントを解説します。せっかく高機能なSFAツールを導入しても、現場で活用されなければ意味がありません。導入の失敗を防ぎ、SFAの効果を最大化するためにも、次のポイントを押さえておきましょう。事前に導入目的や運用ルールなどを明確にすることで、ツールの導入に後悔するリスクを抑えられるでしょう。
なお、SFAとして知名度が高い「Salesforce(セールスフォース)」の導入方法を知りたい方は、こちらの記事をご確認ください。
Salesforceを導入するときのポイントは?導入のフローもご紹介>>
導入時のポイント
SFAの導入目的を明確にする
SFAの導入を考え始めたら、まずは営業活動における課題を明確にし、解決につながる目的を設定しましょう。目的が曖昧なままSFAを導入した場合、ツールの形骸化により、スムーズな定着化が図れない可能性があります。
例えば、「営業日報の作成時間を一人あたり30分削減する」「休眠顧客への再アプローチ率を15%向上させる」など、定量的で具体的な目標を設定することが重要です。
その際にポイントとなるのが導入を検討している段階から、現場担当者を交えて話を進めることです。上層部と現場との間で、SFAを導入する目的について共通認識を持つことで、「上層部の判断でツールを導入したものの、現場担当者からすると使いにくい」といったトラブルを回避できます。
業務フローにツールの活用を盛り込む
SFAを導入する最大の難関は、ツールをいかに定着させるかです。各担当者が自発的にSFAを使用する環境を作るには、業務フローのなかに「SFAを利用しなければ実行できないタスク」を組み込むと良いでしょう。
ツールを使うことが目的化しないよう注意が必要です。既存の業務フローをSFAに合わせて無理やり変えるのではなく、SFAを活用することで「どの業務が」「どのように効率化されるのか」を現場の担当者とすり合わせながら、自然に組み込んでいくことが定着の鍵となります。
例えば、見込み顧客とのファーストコンタクトを終えた段階で、システムにデータを入力しないと、次のフェーズへ進めないようなフローを構築するといったイメージです。システムへのデータ入力が必須になることで、各担当者がおのずとツールを利用する土台が形成されます。
他のツールとの連携を考える
SFAの多くは、CRMやMA、BI(ビジネスインテリジェンス)ツールなど、役割や機能が異なる幅広い外部システムと連携できます。複数のシステムを手当たり次第に連携すると管理が煩雑になるため、連携が必要なシステムの種類や、対象となるデータの範囲などを導入前に決めておくことが大切です。
基幹システムなど、大量のデータを扱うシステムをリアルタイム連携したい場合は、データ連携ツールを活用してみてはいかがでしょうか。
パナソニック インフォメーションシステムズが導入を支援している「ASTERIA Warp(アステリアワープ)」は、100種類以上のシステム同士の連携に対応しているほか、ノーコードで連携フローを構築できます。気になった方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
No.1パートナーとしての20年以上の経験と実績を持つパナソニックISのASTERIA Warpデータ連携支援>>
運用時のポイント
スモールスタートで進める
SFAには、必要に応じてさまざまな機能を拡張できるメリットがあります。しかし、最初から機能を増やしすぎると操作方法が複雑になり、定着しにくくなる可能性があります。
導入時にはスモールスタートで進めることを意識し、段階的に必要な機能を拡張すると良いでしょう。多くのSFAには無料プランや、導入しやすい価格で設定された有料プランが用意されているため、まずは基本的な機能のみで運用を開始することをおすすめします。
データの入力項目を増やしすぎない
データの入力項目が多すぎて担当者の負担が増すと、システムが利用されなくなってしまいます。ツールによっては、項目を自由にカスタマイズできる場合もありますが、まずは必要最低限の項目数でSFAの使用を習慣にすることを優先しましょう。
SFAを導入して営業活動を円滑に進めよう
SFA(営業支援ツール)は、営業活動の属人化を防ぎ、データに基づいた戦略的な営業を実現するための強力なパートナーです。案件管理や行動管理、売上予測といった幅広い機能が搭載されており、ツールの活用によって営業活動の効率化へと結び付きます。今回紹介したSFAの特徴や導入時のポイントを参考に、自社に合ったツールを検討してみてはいかがでしょうか。
数あるSFAのなかでも特におすすめなのは、業界トップシェアを誇るSalesforceです。Salesforceには、今回紹介したほぼすべての機能が搭載されており、多様な外部システムとの連携にも対応しています。
当社パナソニック インフォメーションシステムズは、Salesforceのコンサルティングパートナーを務めており、スムーズな導入を支援しています。定期的に開催しているオンライン個別相談会では、営業部門におけるお悩みのヒアリングから、Salesforceに関するご質問まで、幅広くご相談いただけます。ぜひお気軽にご参加ください。
「Salesforceの導入・活用に関するオンライン個別相談会」の詳細はこちら
▼こちらの資料もオススメです